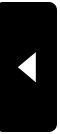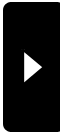袋井お茶大文化祭~BANCHA TEN~のご案内②
2022年11月01日10:00
カテゴリー
2022年12月4日(日)に、袋井市のお茶施設「香りの丘 茶ピア」にて、袋井お茶大文化祭~BANCHA TEN~ を開催します。
当イベントは、晩茶、番茶をメインにしたものとなります。
ところで、BANCHAやTENとは? なぜアルファベット表記なのでしょうか。
本日はそのご紹介をいたします。
まずは、BANCHAに込めた意味からです。それは次のような意を込めております。
BANCHA・・・晩茶(ばんちゃ)、番茶(ばんちゃ)、飯茶(ばんちゃ)、伴茶(ばんちゃ)の意
参考までに、各先生方の「ばんちゃ」の定義を確認します。
******************************************
晩茶とは
松下智(元愛知大学国際コミュケーション学部教授 / ふじのくに茶の都ミュージアム客員研究員)
茶は、本来自然の山野に自生する茶樹の葉を利用してきたもので、茶畑として人工の管理に入ったのは、後世のことになる。その自然物としての茶の姿を留めているのが、「晩茶」 である。
晩茶と同一発音のものに「番茶」があるが、後者の番茶は、別名「番刈晩茶」 と云うわけで、五月の新茶時に篩分けした時に残ったものである。したがって、晩茶とは根本的に異なるものである。
晩茶は五月頃の新芽の摘採は行わず、そのまま生長を続けさせ、八月頃の生長した茶の芽、葉と枝、共々刈り取って利用する。七~八月の夏期の刈り取りをさらに延長して、真冬に刈り取るものもある。
「日本の晩茶 その種類と分布」(2000年)
******************************************
茶の多様性
小泊重洋(元お茶の郷博物館 館長)
「番茶」は、昔から人口に膾炙(かいしゃ)した極めて庶民的な響きのある言葉であり、お茶である。これは、その成り立ちからして合点のいくところである。しかし、最近の豊かさに埋もれて省みられなくなりつつある物のひとつでもある。地方の伝統的な番茶の復権は困難かもしれないが、茶の多様性を考えるときもう一度目を転じても良いお茶ではないだろうか。
「緑茶通信2004年1月号」
*******************************************
飯茶であり伴茶である、それが“ばん茶”
小川八重子(1927-1995、常茶研究家)
おばん茶というのはふだんの暮らしの中ではぐくまれてきたお茶であり、古くから極(ごく)あたりまえという意味に使われている。“日常茶飯”という言葉があるが、文字通りそのお茶であると思う。それぞれの土地でその郷土の食事と共にあったお飯茶でありお伴茶であった。作り方さまざま、飲み方さまざま、形、色、香り、味、さまざま、極めて郷土色豊かな茶である。
雑誌「サライ」1993年9月16日号
*******************************************
つぎに、TENについてです。それは、次のような意を込めております。
TEN・・・・・店(てん)、展(てん)、巓(てん)の意
様々な意味を込めた想いに、作り手の想いと提供者の想いを込めて、イベントを運営いたします。
どうぞ皆さま茶ピアまでご来場くださいませ。

当イベントは、晩茶、番茶をメインにしたものとなります。
ところで、BANCHAやTENとは? なぜアルファベット表記なのでしょうか。
本日はそのご紹介をいたします。
まずは、BANCHAに込めた意味からです。それは次のような意を込めております。
BANCHA・・・晩茶(ばんちゃ)、番茶(ばんちゃ)、飯茶(ばんちゃ)、伴茶(ばんちゃ)の意
参考までに、各先生方の「ばんちゃ」の定義を確認します。
******************************************
晩茶とは
松下智(元愛知大学国際コミュケーション学部教授 / ふじのくに茶の都ミュージアム客員研究員)
茶は、本来自然の山野に自生する茶樹の葉を利用してきたもので、茶畑として人工の管理に入ったのは、後世のことになる。その自然物としての茶の姿を留めているのが、「晩茶」 である。
晩茶と同一発音のものに「番茶」があるが、後者の番茶は、別名「番刈晩茶」 と云うわけで、五月の新茶時に篩分けした時に残ったものである。したがって、晩茶とは根本的に異なるものである。
晩茶は五月頃の新芽の摘採は行わず、そのまま生長を続けさせ、八月頃の生長した茶の芽、葉と枝、共々刈り取って利用する。七~八月の夏期の刈り取りをさらに延長して、真冬に刈り取るものもある。
「日本の晩茶 その種類と分布」(2000年)
******************************************
茶の多様性
小泊重洋(元お茶の郷博物館 館長)
「番茶」は、昔から人口に膾炙(かいしゃ)した極めて庶民的な響きのある言葉であり、お茶である。これは、その成り立ちからして合点のいくところである。しかし、最近の豊かさに埋もれて省みられなくなりつつある物のひとつでもある。地方の伝統的な番茶の復権は困難かもしれないが、茶の多様性を考えるときもう一度目を転じても良いお茶ではないだろうか。
「緑茶通信2004年1月号」
*******************************************
飯茶であり伴茶である、それが“ばん茶”
小川八重子(1927-1995、常茶研究家)
おばん茶というのはふだんの暮らしの中ではぐくまれてきたお茶であり、古くから極(ごく)あたりまえという意味に使われている。“日常茶飯”という言葉があるが、文字通りそのお茶であると思う。それぞれの土地でその郷土の食事と共にあったお飯茶でありお伴茶であった。作り方さまざま、飲み方さまざま、形、色、香り、味、さまざま、極めて郷土色豊かな茶である。
雑誌「サライ」1993年9月16日号
*******************************************
つぎに、TENについてです。それは、次のような意を込めております。
TEN・・・・・店(てん)、展(てん)、巓(てん)の意
様々な意味を込めた想いに、作り手の想いと提供者の想いを込めて、イベントを運営いたします。
どうぞ皆さま茶ピアまでご来場くださいませ。